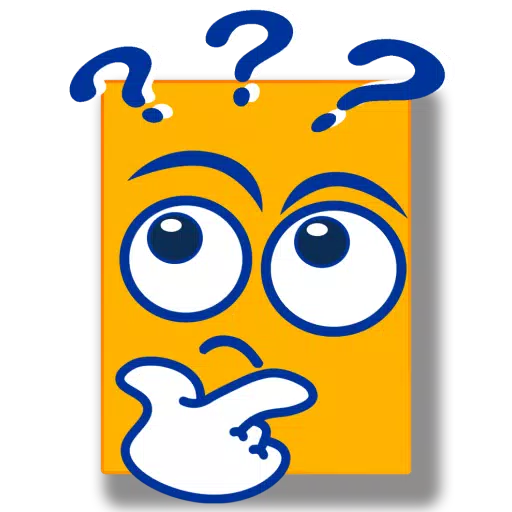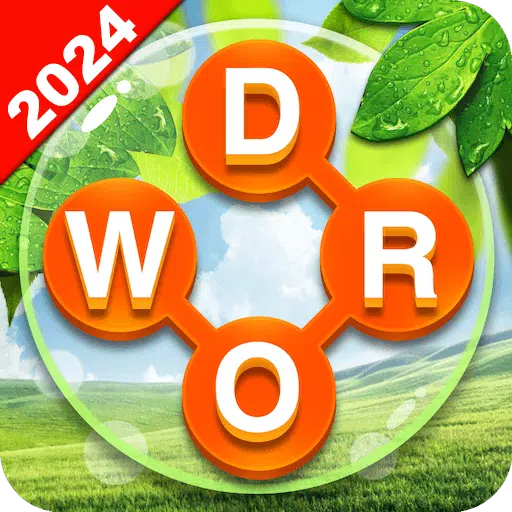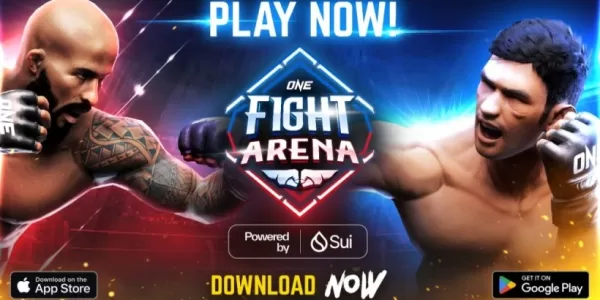CDプロジェクト・レッドは卓越したゲーム制作で名声を築いてきた。発売から10年経った今でも『ウィッチャー3』は史上最高のRPGの一つとして称賛され、『サイバーパンク2077』は大規模なアップデートにより、細部までこだわったオープンワールドの傑作へと成長した。これらの作品だけで、同スタジオは同等に魅力的な作品群を擁するゲーム開発の世界的リーダーとしての地位を確固たるものにしている。しかし、CDプロジェクト・レッドの作品を真に際立たせている要因とは何だろうか?
CDPRの洗練された体験には複数の要素が寄与しているが、彼らのRPGを真に引き立てているのは、個々の要素がシームレスに組み合わさり、没入感ある一体感を生み出す点だ。この真実味はダイナミックなストーリーテリングから生まれている——プレイヤーの選択によって物語や世界、キャラクターが変化する。多くのスタジオが類似の枠組みを採用しているが、CDPRほどの精度で実行しているところはほとんどない。
「他のAAA級RPGをプレイする際、よく開発ツールの制約に気づきます」と語るのは、CDPRのフランチャイズコンテンツ戦略リーダー、パトリック・ミルズ氏。「デザイナーのビジョンは感じられるものの、その制限が野心不足や怠慢ではなく、ツール自体の限界によるものだと分かるのです」

CDPRは自社開発ツールに多大な投資を行い、創造的なビジョンを実現するためREDengineを4つのバージョンにわたって開発してきた。この特注技術により、プレイヤーの行動が世界に意味ある影響を与える相互接続されたゲームプレイシステムが可能になった。後のバージョンではさらに大胆なクエスト設計が可能となり——『ウィッチャー3』の「調査・戦闘・対話」の三位一体は、『サイバーパンク2077』ではハッキングやステルス、サバイバルホラーを彷彿とさせる『ファントム リバティ』の最終局面へと進化した。
「大規模RPGにおいて多様性は単に有益というだけでなく、不可欠な要素です」とレベルデザインリーダーのマイルズ・トストは説明する。「新しいメカニクスやシステム的な柔軟性がなければ、強い物語があってもプレイヤーは離れていってしまうでしょう」
この哲学はストーリーテリングにも及ぶ。CDPRのクエストは予測可能な結末を避けており——一見単純な任務でさえ「破壊テスト」が行われ、テストプレイヤーがあらゆる考えられるアプローチを試す。得られたデータはクエストを洗練させ、プレイヤーの創発的行動に対応することで、自然な感じのする結果をもたらす。
キャラクタービルドが『サイバーパンク』のゲームプレイに影響を与える一方、CDPRは物語上の重大な選択肢で真価を発揮する。道徳的な二者択一ではなく、『ウィッチャー2』での政治的運命の決定や『ファントム リバティ』でのソングバードとリードの選択のように、遅延した影響を伴う複雑なトレードオフを提示する。これらの決断が共感を呼ぶのは、事前に文脈が丁寧に確立されているためだ。

「私たちはプレイヤーに、たとえ結果が苦いものであっても選択が重要だと感じてほしいのです」と『ウィッチャー4』ディレクターのセバスチャン・カレンバは説明する。このこだわりには時として構造的な調整が必要で——『サイバーパンク』では当初微妙な結果だったものが、ナイトシティの密集した環境でプレイヤーが因果関係を見逃していることに気付いた後、『ファントム リバティ』では増幅された。
しかし真に影響力のある選択肢には、設計と同じくらい実行が重要だ。「脚本家は対話を通じて感情を喚起し、アニメーターやシネマトグラファーはそれらの瞬間を説得力あるものにしなければなりません」とクエストデザイナーのパヴェウ・ガスカは指摘する。個人的な利害関係が理論上のジレンマを悲痛な決断へと変える——これはCDPRがキャラクター描写に適用している原則だ。

CDPRが『ウィッチャー4』でUnreal Engine 5への移行を進める中、チームは野心的な目標と技術的現実のバランスを取らなければならない。「拡張コンテンツの開発は基本ゲームよりもスムーズなことが多いです。核心的な疑問が解決されているからです」とトストは語る。課題は、新しいツールを習得しながらその明確さにより早く到達すること——このプロセスにはEpic Gamesとの密接な連携が必要だ。
「プレイヤーの主体性は変わらず私たちの北極星です」とカレンバは強調する。「私たちは物語的にも機械的にもより深いロールプレイングツールを提供し、プレイヤーが本当の意味で自分の体験を形作れるようにしたいと考えています」。『ウィッチャー3』のレガシーを超えるのは容易ではないが、『ファントム リバティ』が『サイバーパンク』の立ち上げから回復を見せたことが何らかの示唆を与えるなら、CDPRは共感を呼ぶ選択肢を提供するという誓いを堅持していると言えるだろう。
 家
家  ナビゲーション
ナビゲーション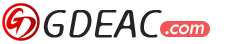






 最新記事
最新記事






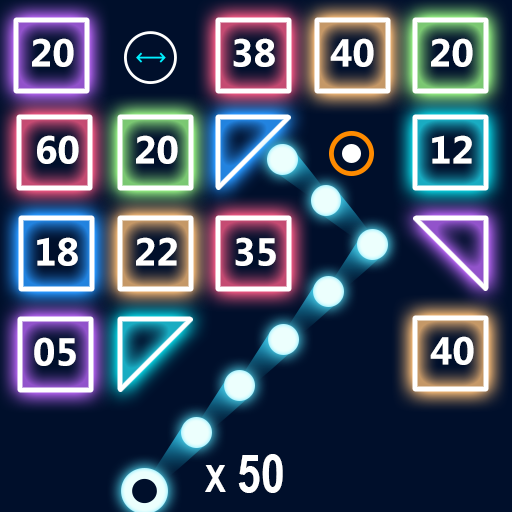



 最新のゲーム
最新のゲーム